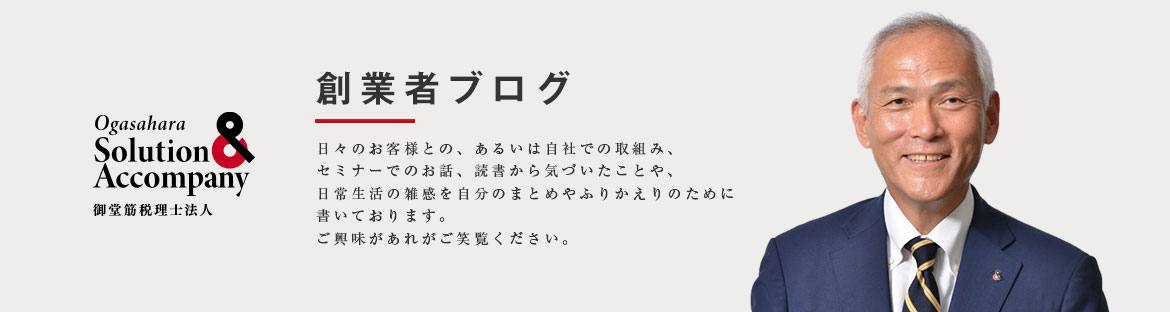ものまねから自分の力で考えるへの進化
2021.12.06
読書と修養
『プラトンへの序言(PREFACE TO PLATO)』という本がある。なんか気になってページを開けてみたら、ついつい途中でやめられず、最後まで読んでしまった感がある本である。封を開けてしまったかっぱえびせん、といったような感じである。
しかし、この本、なんか気になって途中で放り投げなかったのはそこに気づきがあったからである。それは何だったのか?
この本で著者は、プラトンが著書『国家』において、音楽を教育の敵だと激しく非難したことを取り上げてる。ところでこの話、実際、僕のようなアホなどが読んでいても「なんでやのん?」くらいの鈍感な感じ方であった。いな、多くの読者がそうなのではないかと推察する。
ところで、プラトンなどアテネで哲学(フィロソフィア)や弁論術(ディアレクティゲー)が花開く以前の時代のギリシアの記念碑的な叙事詩として、ホメーロスの『イーリアス』、『オデッセイ』やヘシオドスの『神統記』、『労働と日々』がある。
ホメーロスの『イーリアス』は、アガメムノン率いるアカイア軍(ギリシア側)と、プリアモスを家長とするトロイア(小アジア側)との10年にわたる戦いの物語である。発端はプリアモスのバカ息子パリスが、アカイア側の絶世の美女、一族の嫁、ヘレネ―(これもおバカさん)を誘惑し、連れ去ってしまったことにある。メンツを丸つぶれにされたアトレウスの末裔たち、それを取り戻さなければ面目がたたぬと、まあこうというわけである。なんともしょうむない話ではある。だが、人間って、歴史ってそんなもんだろう。
話は、アガメムノンと、彼によってせっかく得た戦利品の美女の返還を強要された、かの半神の勇者アキレウスとの対立に始まる。
怒ったアキレウスが参戦拒否して戦線離脱し、代わりに行ったパトロクロスがプリアモスの息子、ヘクトルとの戦いに敗れて戦死する。
親友の死の知らせを聞いてさすがついに身体を起し、復讐のために戦場に復帰したアキレウスとヘクトルとの一騎打ち、そしてヘクトルの死、その死体を引きずりまわすアキレウス、息子の引き取りを依頼する父プリアモス。憤怒と愛惜の比類なき描写。
最後に、智者オデュッセウスの奇策による木馬を使ったトロイ攻撃と、その結果としてのプリアモス側の悲惨な破滅、さらにその後潭。
血沸き肉躍り、また親子、一族、敵味方の戦いと許し、愛と憎悪を語って、心底から心をゆさぶってやまない長大叙事詩である。
さらに『オデッセイ』は、そのトロイ戦争の後、参戦していた知恵者オデュッセウスが、幾多の苦難を乗り越えて故郷イタカに帰郷する話である。
どちらもすばらしい世界最高峰の叙事詩であり、西洋のその後の文学、哲学、日常のあらゆる表現や会話に無数に引用されてきたエピソードが満載されている空前絶後の作品である。
さてそれらとは別に、ホメーロスの少し後に出たとされるヘシオドスによって語られた『神統記』と『労働と日々』という叙事詩がある。『神統記』は、それぞれ様々な自然現象や人間の感情や文化を体現し司っているというオリンピアの神々の系譜を語り、『労働と日々』は、当時の農業への従事のしかたを人々に教えている作品である。これらもまた、ホメーロスとは趣きは異なるが、人びとに教え諭すこと膨大である偉大な作品である。
さて、これらの作品は、それらをそのまま読むと、それはそれだけのことなのだが、ハヴロックは、その背後にあるものを洞察する。
プラトン以前のギリシアには文字がなかった。アルファベットが東方から伝わって、彼らが文字を持った(Alphabetaized)のは、おそらくプラトンの1,2世紀前のことだろう。
だからプレ・プラトン時代、ギリシア人たちは、これら物語の口誦によって、人びとが持たなければならない民族の文化の継承に必要な知識、倫理を人民に教え、後代に伝えたのだという。ただしそこには為政者の、あるいは製作者の意図があったという。これがハヴロックのすばらしい推理なのである。
こういう観点からさまざまな叙事詩といわれるものを見ると、たとえば、イーリアスやオデッセイは、義理と人情、戦いと義務といった社会規範を人々の心に植えつけるためのものだったのであり、また、神統記や労働と日々は、人びとに自然現象や農事のことを教える百科事典(エンサイクロペディア)の役割を果たしたというのである。
なにしろ文字がないのだから、人びとに脳裏にそれらのことを記憶させ、植え付けるためには、ボディランゲージ、ダンスや、リュラなどの音楽にサポートされてパフォーマンスされ、記憶の手助けをしたという。われわれ人間はそうした支援を受けてこそ、生きていく上の知識をより容易に効果的に記憶できるからだ。
結局、それらの叙事詩は必要なことを記憶させる教育のための手段(メディア)だったのだ。これによる学習をミメーシス(模倣)という。そこから生まれる精神は、ただ伝統的なものを無批判にマネをして受け入れるというものにならざるを得ない。そこには、個人としての批判的精神はありえない。プラトンが論難したのはまさにこの点であった。
彼は、文字ができて、人びとの思考活動が、弁論術の華が開いた、BC5世紀から4世紀、アテネの絶頂期に生きた。そこでは、すでに文字によって触発されて、弁論の文化が花開いていた。ギリシア人たちは徹底した言語の文化を持っていた(そして、それはその後のヨーロッパの文明、文化の基となった)。
日常の生活においても、ソフィストたちが大枚な錢を取って、若者に絶対に議論に負けない方法を教えていた。それは往々にして、つまらぬ牽強付会の論であった。
それに眉を顰め、鉄槌を下したのが、かのソクラテスである。彼はそれによって為政者たちから訴追され毒杯を飲み干して慫慂として死の床についた。それを目撃して精神につよい衝撃と影響を受けた愛弟子プラトンは、その師の口を借り、彼の思想を引き継いで多くの対話編を書いた。その一つが『国家』である。
プラトンはその後、自らの思想を教える学園、アカデメイアを創ったが、彼の教育の方法論は、ソクラテスのように、本質的質問によって、相手の、たんなる思い込み、あるいはシングルループの思考回路を揺り動かして、人びとに自分自身の脳力でもって、ものごとを深く、独自に考えさせることであった。これをフィロソフィア(智を愛する)と表現した。フィロソフィー、つまり哲学の宣言であった。
それは、過去の出来事をかたる『過去形』の思考から、自然や人間の実態とあるべき姿を語る『現在形』の思考への転換であった。『男性名詞・女性名詞』の表現から、『中性名詞』への転換であった。『具体性』から『抽象性』への転換であった。『物語』『追悼演説』から『討論』『対話』『演繹』への転換であった。それは人間が、『没個性的存在』から脱皮して、『一個性』として、Individualとして確立した歴史的瞬間であったのである。
プラトンは、単なる思い込み=ものまねの文化の悪弊を罵倒し、若者たちに自分の力で分析し、思考し、ふり返り、意見形成をすることを求めたわけである。それゆえ、音楽を目の敵にしたのである。
そしてプラトンはいう。『最高の音楽は、哲学である』と。なるほど論難する相手の特徴を言葉ごと取り込んだ彼の気概と宣言であろう。
この本の話の主題はそれだけである、著者は300ページを使って、執拗にこの発端、経緯、結末、深層をひもといてゆく。そこが実に興味深いと言わざるを得ない。
読みながら、そこから僕はずいぶん多くの、日常、自分が感じていることとひもづけて、自分の考えをさらに腑に落とすことができた。
・ やはり、思考は人の受け売りでなく、なんでも自分で考えて、自分のものにしなければならないということ
・ 他人にもそうしてもらうには、ソクラテスが常用したように質問という手段がしこたま重要だということ
・ 他者を説得しようとするならば、物語を語るのは大変に効果的であるということ
・ 人に何かを伝えたり、いろいろなコミュニケーションをするためには、
どのようなメディアが利用可能なのか、またどのようなメディアがよいのかを考えなければならない
といったようなことだ。
これらのことは、コンサルタントとしてお客様の企業を高業績化していくために、とても本質的に重要な精神的態度だと思っているものだ。
実際に、経営計画を作り、経営を数値制御し、それらを基に月々経営を進めた結果を検証し、お客様の反応や仮説の妥当性などを考えるとき、僕は、メンバーの人たちに自分はどう思ったか、どう考えるのか、それはなぜなのかということを執拗に問うていく。その場合に、上に掲げたことを強く確信するわけである。
それゆえ、はからずもこの本を最後まで読まされてしまったということだった。そういう意味で、この本はわたしにとってはとても為になる豊潤な作品であった。
つまらないお話にお付き合いいただきありがとう。